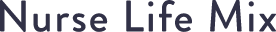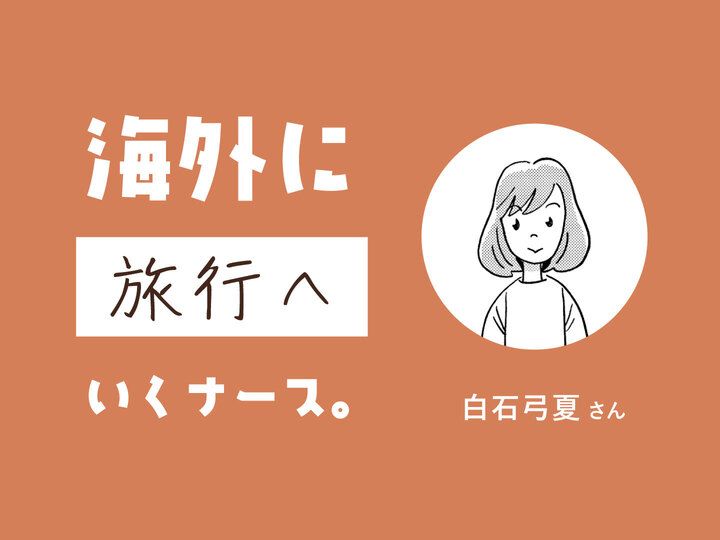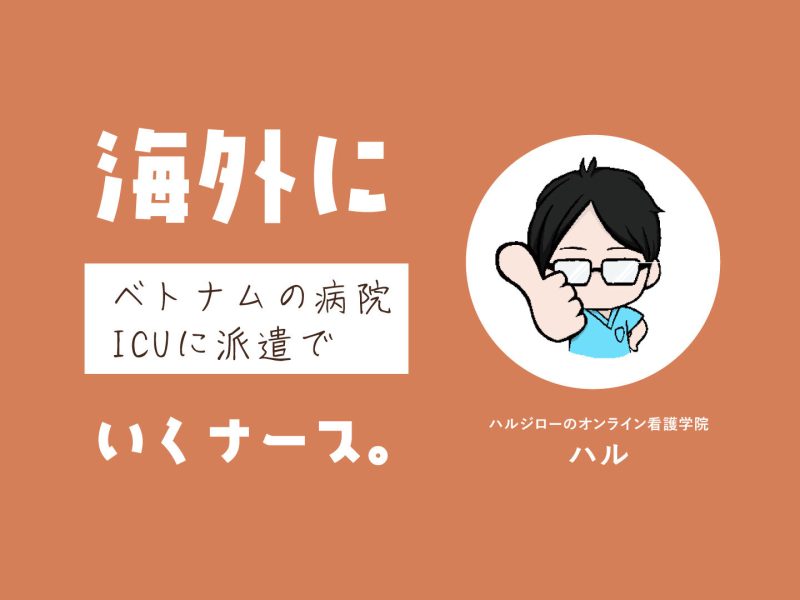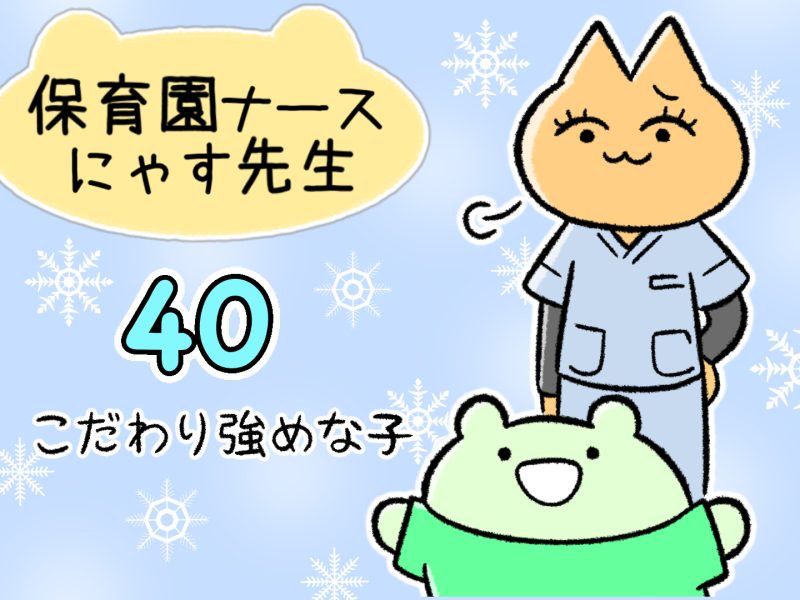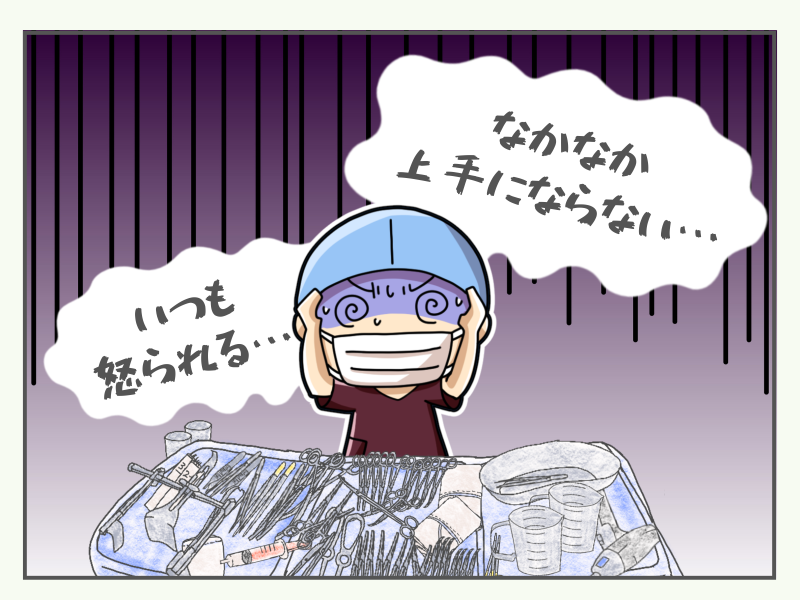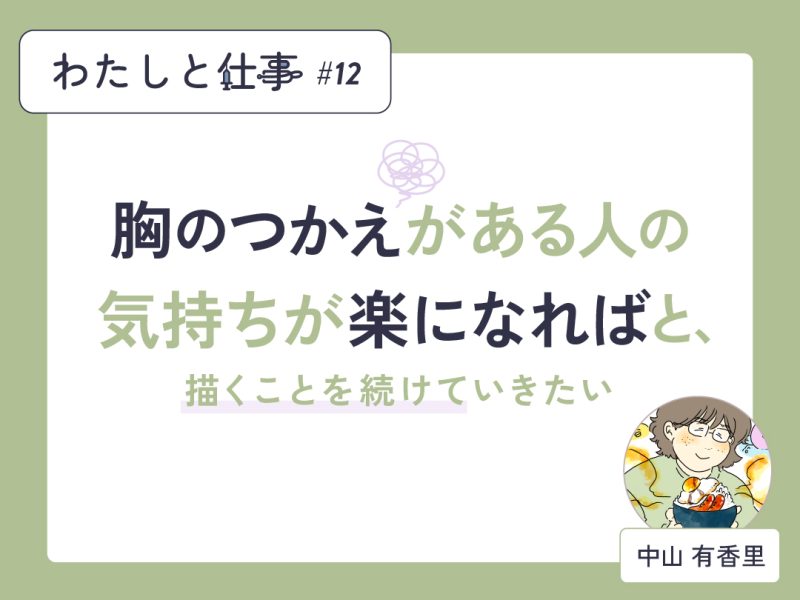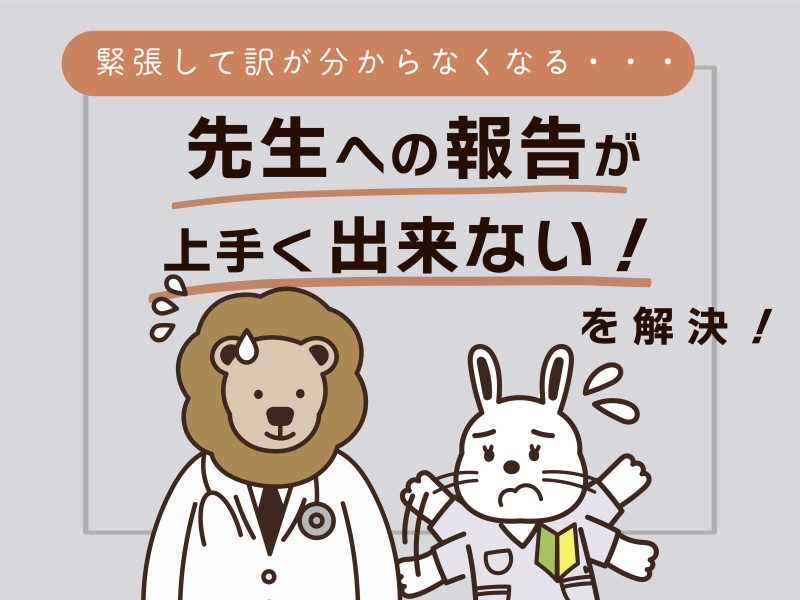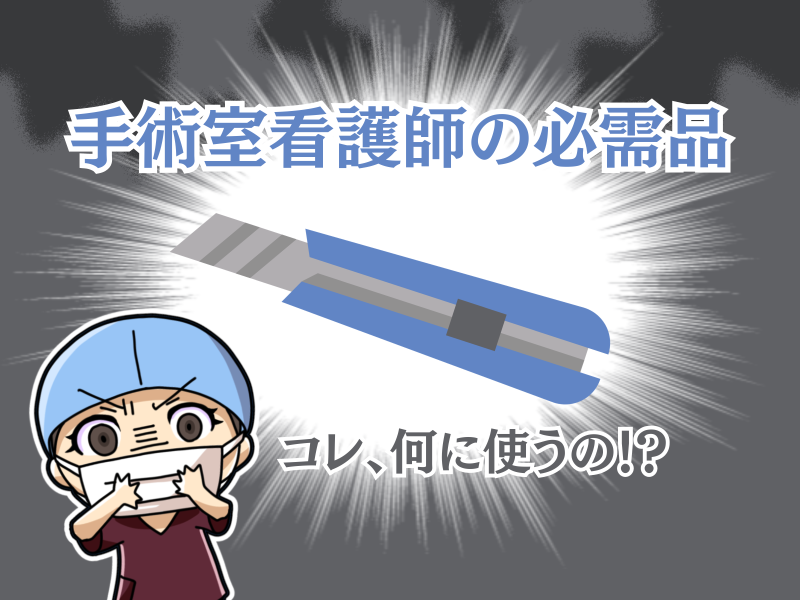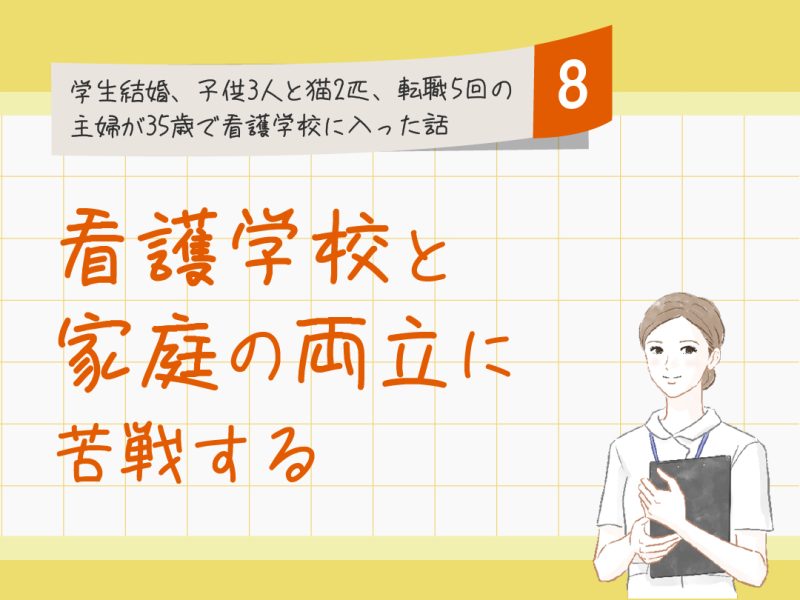海外にいるナース〜イギリスの病院で働く私が感じたカルチャーショック5選!〜
公開:2025.03.27

前回は、私がイギリスで現在の役職に就くまでのお話しをしましたが、今回はイギリスの病院で働き始めてから感じた数あるカルチャーショックの中から厳選して5つ紹介します!(あくまで私が日本とイギリスで看護師をする中で感じたことを比べていますので地域や職場にもよることをご了承ください。)
1.人権と自由の考え方が違う!?
イギリスでは、個人の自由や人権をとても大切にする傾向があります。意思決定能力があればリスクを伴うことを理解していれば治療を拒否したり外でタバコを吸ったり。中でも一番驚いたことは圧倒的に身体拘束をしないことです。日本でも身体拘束を減らす努力がなされていますが、イギリスで私が見てきた一般病棟では限りなくゼロ近いです。時折ミトンを使うことはあるものの、手抑制や体幹抑制などを使うことは許されない姿勢です(もはや病棟に置いていません)。それが可能である2つの理由について考えてみました。
1つめは人員配置。
不穏や認知症などのリスクのある患者さんには看護助手(HCA)が1:1で付き添うスペシャリングというケアが行われています。この1:1の付き添いがあることで不穏が落ち着くこともありますし、徘徊傾向のある方も安全に徘徊できます。このスペシャリングでさえも自由抑制の一部と捉えられているので、患者さんの精神判断能力のアセスメントの書類記入、自由抑制の必要性と許可を求めるフォームを記入し監督機関である地方自治体に提出した上で行います。看護助手が1:1で付き添ってくれるおかげで看護師としては他の業務に時間を割くことができる環境です。それでも手が追えなかったり暴力などがあればセキュリティスタッフが助っ人で来てくれます。
2つめは一般病棟の高齢者の割合が圧倒的に少ないということ。
日本は令和3年の時点で65歳以上の入院患者が80%に対して、イギリスは40%というデータもあります。私の感覚としてもイギリスで寝たきりの高齢者を病院で見かけることはあまりありません。大きな要因として延命やDNARについての考え方の差があると考えます。イギリスではDNRは医療的判断とされていて、CPRをしても助からない/心身のダメージが大きいと判断されれば医師がDNRの指示を出します(ここは逆に個人の自由は無いようです)。延命に対して否定的な考えを持つ人も多いです。
日本でも2024年に強制社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、身体抑制予防が注目を浴び始めていると聞きました。認知症の父と精神疾患のある兄を持つ身として治療の現場での身体拘束が日本でも少しでも減ることを願っています。

2.有給がたくさん取れる
イギリスで看護師として働き始めて一番最初に驚いたのは有給の多さでした!年間30日前後(勤続年数による)とることができます。これにプラスして、週3〜4日勤務なので毎週4日間有給を使うと合計42日程度休みが取れる裏技も。しかも希望した休日が取れることがほとんどな上、上下関係もあまりないので先輩が優先ということもありません。このおかげで、大好きな日本にほぼ毎年帰ることができています。有給の他にも、病欠休暇や子供の看病休暇などに給料が発生することにも驚きました。これと同時に、日本人に比べてイギリスで働いている同僚は比較的休むことに申し訳ないという感情を持たないことにも驚きました。これらが可能なのは、休みで空いた穴を埋めるシステムが整っているからだと思います。病院所属の単発勤務専門スタッフ(バンクスタッフ)や常勤スタッフが休みの日に自らバイトで入ることで賄われています。

3.バイタルは看護助手が測ってくれる
イギリスには“Healthcare Assistant(HCA)”という職業があり、日本語にすると「看護助手」に近い立場です。領域にもよりますが、一般病棟ではほとんどの場合、HCAがバイタルサインや血糖値、尿量を測定し記録してくれます。異常があれば報告してくれますし、体位変換や清潔ケア、トイレ介助、食事介助なども主体となってくれます。私も正看護師になる前にHCAとして働いていましたが、HCAの中には私のようにイギリス以外で看護師をしていたことがある人や医学生・看護学生が経験を積むためにバイトしていたり、全く医療知識の無い元スーパー店員の方が転職したりと様々でした。HCAとして働くために必要な知識や技術は、働きながら学びつつ、看護助手向けの研修で補われています。HCAの中には特別な研修を経て採血をしたり静脈留置カテーテル/膀胱留置カテーテルを挿入したり胸腔ドレーン抜去補助をするスキルを持っている人もいます。

4働くモチベーションの個人差が大きい!?
イギリスで働く看護師や看護助手のモチベーションの高さや仕事へのモラルは、日本以上に人によって全然違うと感じています。もちろん、向上心高く仕事をきっちりこなす人もいるのですが、日本のスタンダードと比べると全体的に仕事への熱はあまりないように感じます。日本を出て改めて日本は世界に誇れるホスピタリティやサービス精神があると感じました。それはそれで素晴らしいことですが、イギリスで働く中で少しずつ自分の身を削ってまで仕事に尽くすことなく自分も大切にしてあげることの大切さを学びました。初めは「いかに楽をするか」を大切にしている人たちにイライラしたりぶつかったり、その人の分まで働いてしまったりしていましたが、そのうち他人は他人と割り切るようになったり、看護助手への指示出しの仕方によって動いてくれることを実感して仕事がしやすくなりました。
一番驚いたのは、休みのスタッフの穴埋めのためにきたバンクスタッフが担当患者さんをひと目見て「やっぱやめた」というノリで家に帰ってしまうことがあったり、帰られたら困ることを知って酷い態度をとる人がたまにいることです。

5.多国籍/多民族な人が集まる環境
ロンドン中心の病院ならではですが、想像を遥かに超える規模で多国籍/多民族の環境で働いています。私が勤める医療法人はロンドンで10の病院を経営しており、働くスタッフの国籍数は121カ国にものぼります。スタッフだけでなく患者さんのバックグラウンドも多種多様で、毎日のように新しい国の文化や慣習を学ぶことがあり刺激の連続です。日本で働いている時にはあまり考えることのなかった宗教への配慮、(食事、お祈り、同性のみによる看護の希望、死生観の違い)、清潔概念の違い、痛みのコントロールに対しての考え方など多様性を尊重することへの重要性を学びました。と同時に海外から来た移民看護師として目立つこともなく受け入れられていることにも感謝しています。

おわりに
5つに絞るのはなかなか難しいほど、たくさんの違いやカルチャーショックがあります。興味のある方は私のInstagramで紹介していますので遊びに来てください。
ロンドンでナースエジュケーターをしています。instagramでは日本とイギリスでの看護師経験を比べたり、医療英会話について、多様性や自分らしくいること、メンタルヘルスやマインドセットについて等、様々な発信をしています。不定期でライフコーチや英会話レッスンも行っています。
Nurse Life Mix 編集部です。「ライフスタイル」「キャリア」「ファッション」「勉強」「豆知識」など、ナースの人生をとりまくさまざまなトピックスをミックスさせて、今と未来がもっと楽しくなる情報を発信します。