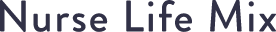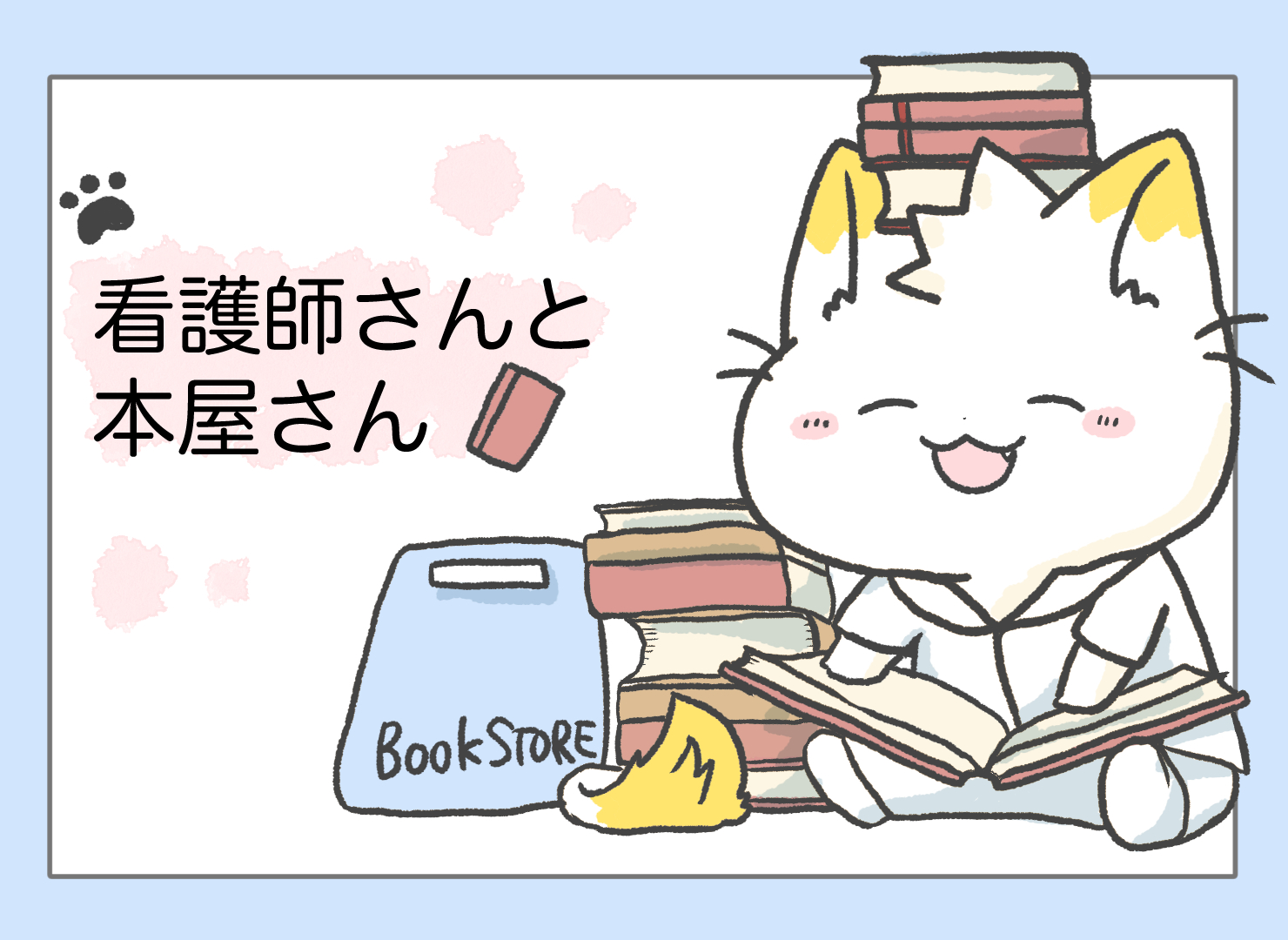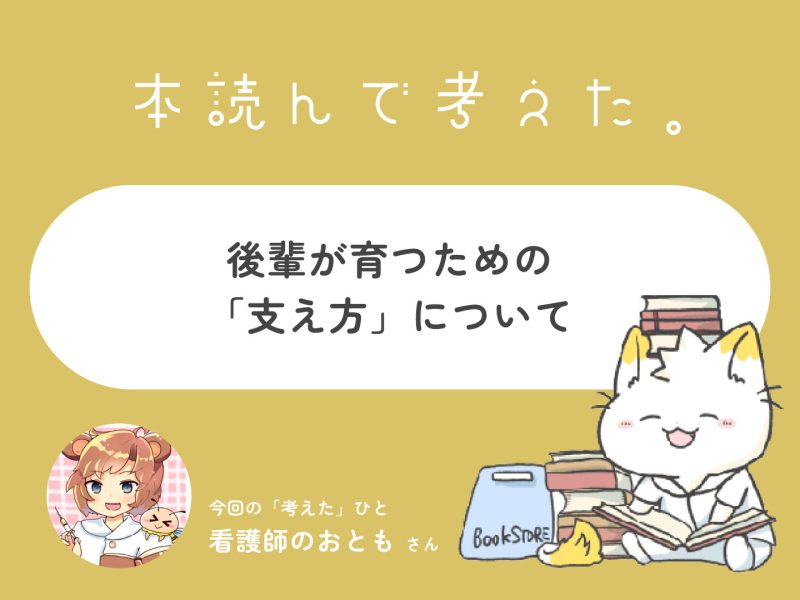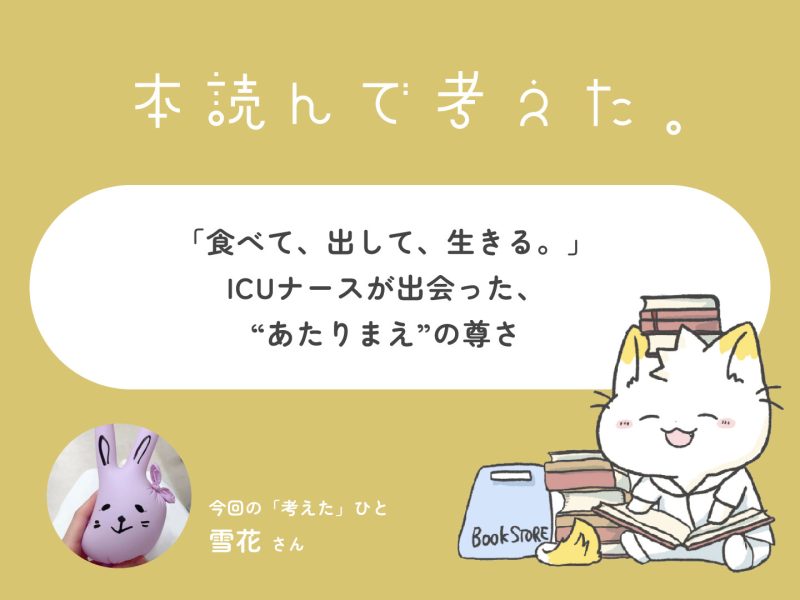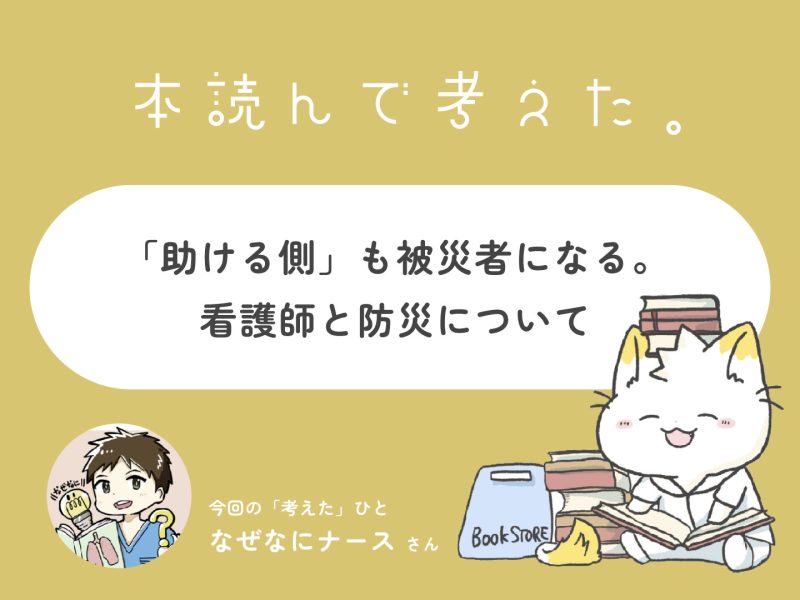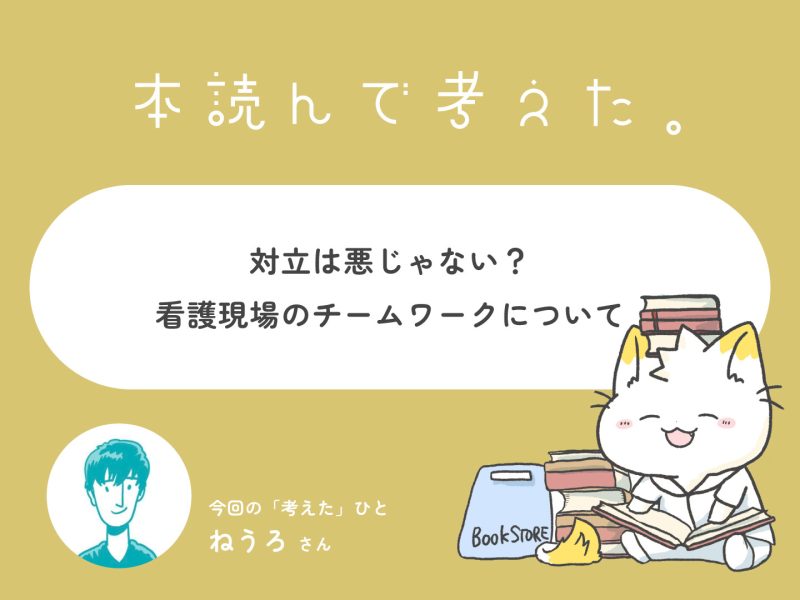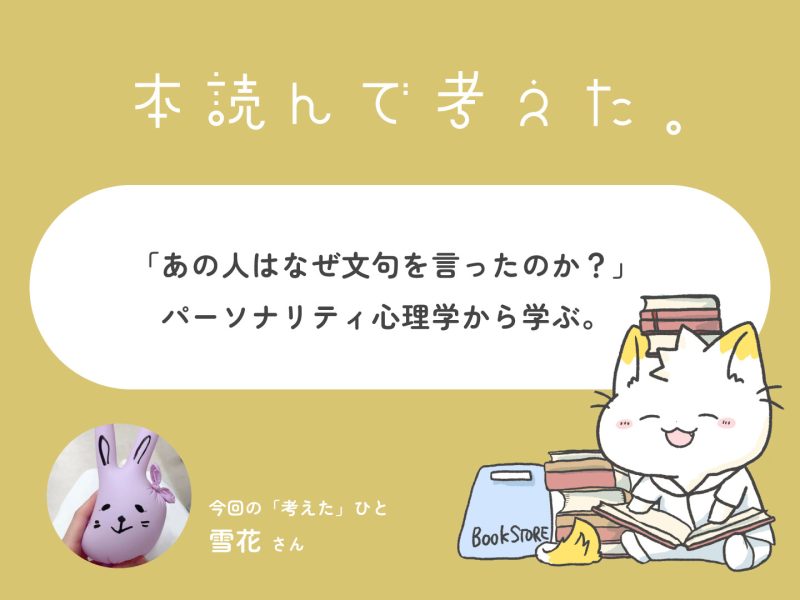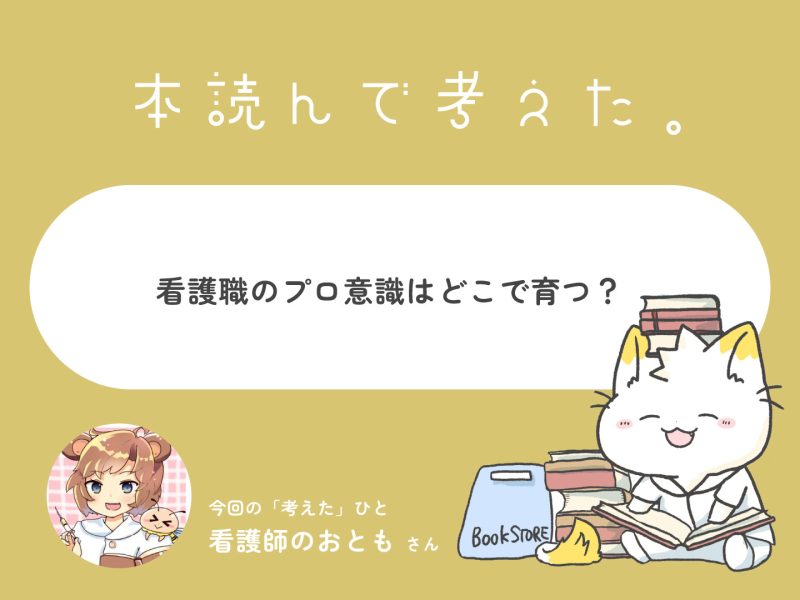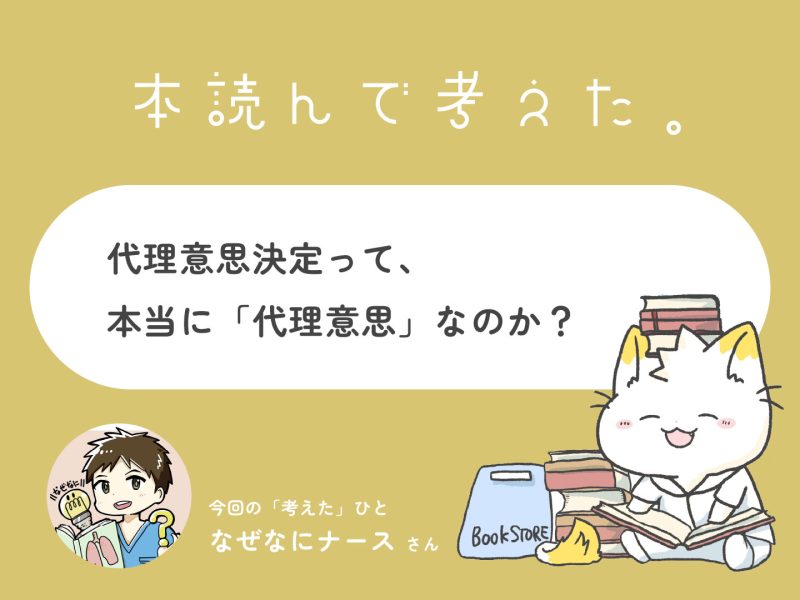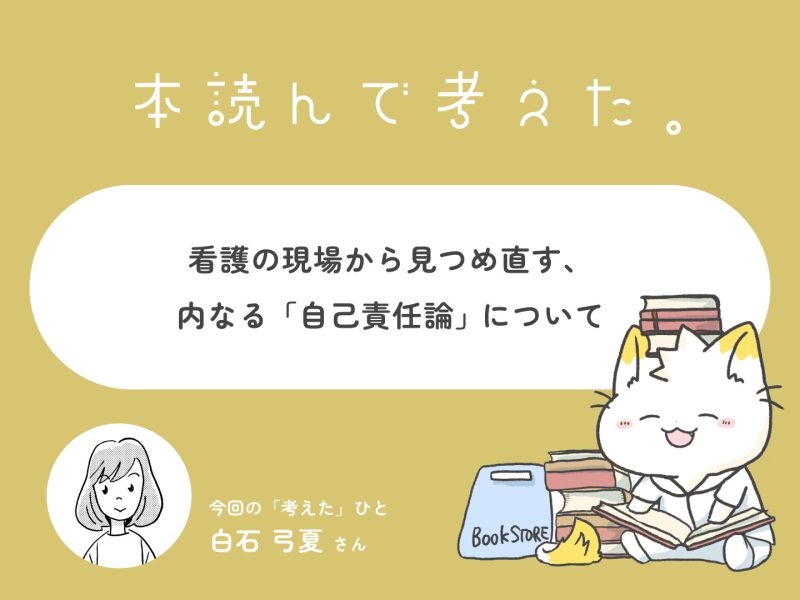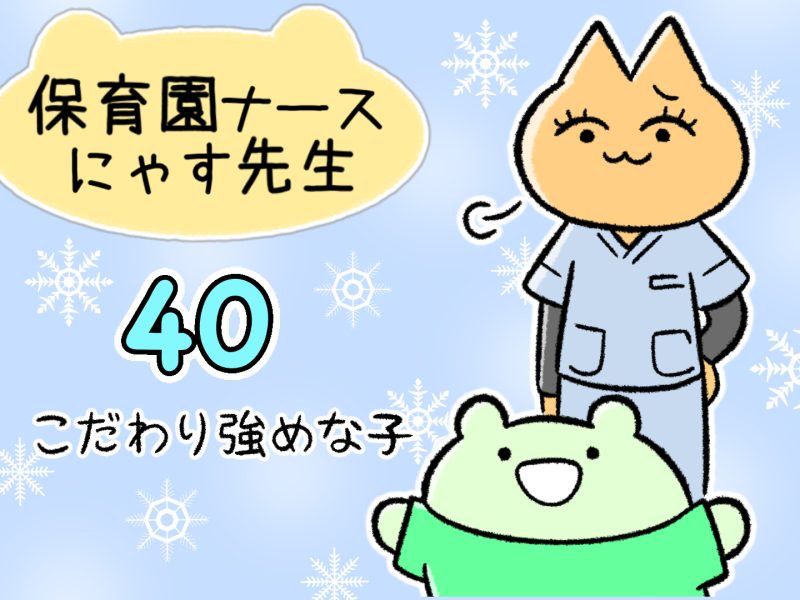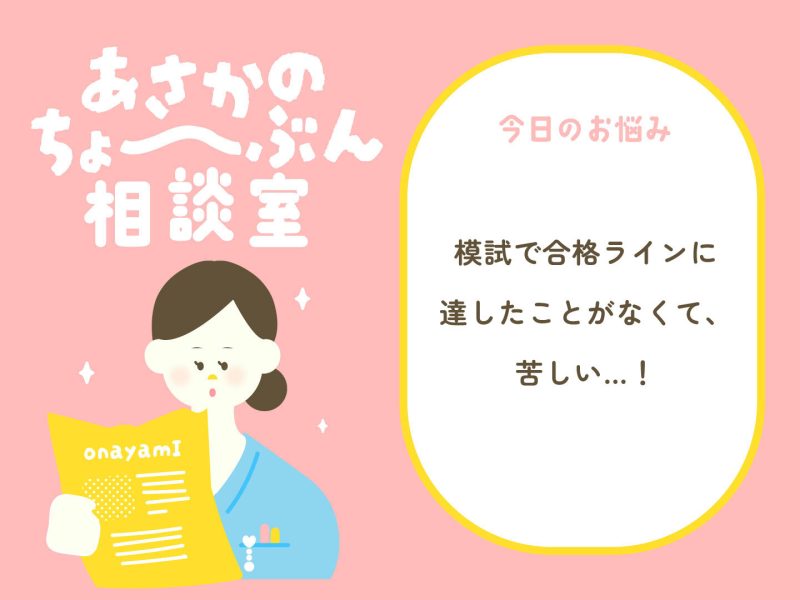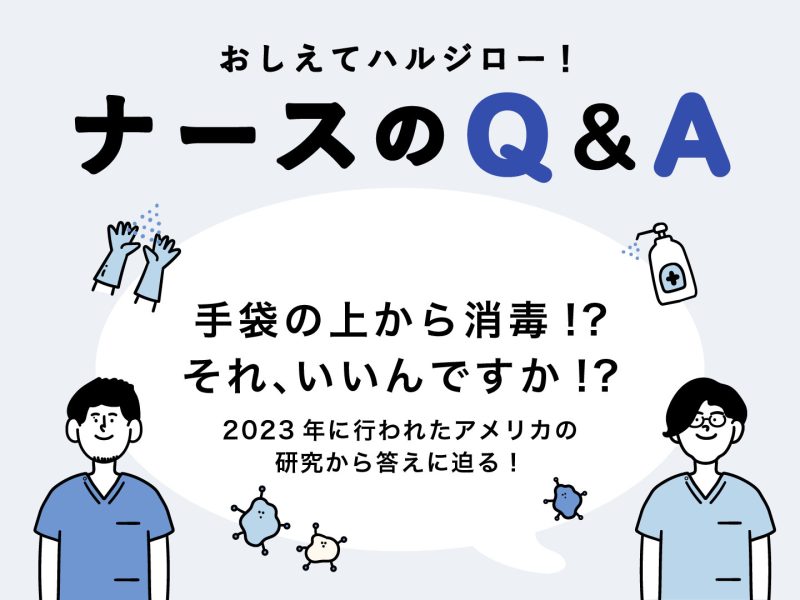患者の“帰りたい”に応える緩和ケアについて、本を読んで考えた。(考えたひと:看護師のかげ)
公開:2025.07.22

今回は「患者の“帰りたい”に応える緩和ケア」をテーマに、看護師のかげさんが考えました。
看護師のかげ
現在は呼吸器センターで働いている病棟看護師。循環器センターや救命救急センターの経験がある。そのほか学生や新人看護師向けの参考書やコンテンツ作りをしている。著書「看護が苦手なかげさんのイラスト看護帖(永岡書店)」など。呼吸療法認定士、終末期ケア専門士。
緩和ケアは、さまざまな診療科で必要なケア
私は今呼吸器センター病棟に勤務しています。そこでは手術をする患者さんもいれば放射線療法や化学療法をなどさまざまな治療を受ける患者さんが入院しています。
そこで外せないものの一つに「緩和ケア※」があります。
私からは仕事で体験した緩和ケアで印象に残ったエピソードとその頃に読んだ本で得た気づきについてお話ししたいと思います。
※緩和ケアとは、生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のQOLを、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである。
(緩和医療学会「WHO(世界保健機関)による緩和ケアの定義(2002)」定訳より引用)
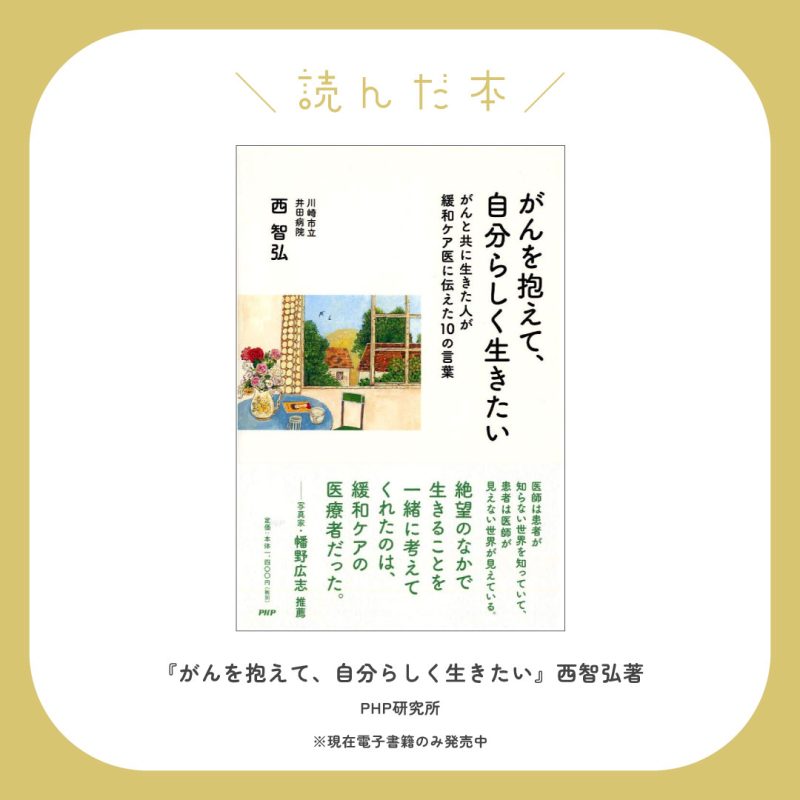
読んだ本:『がんを抱えて、自分らしく生きたい』西智弘著(PHP研究所)※現在電子書籍のみ発売中
「退院?!」と戸惑った私たちと、先生の笑顔
私の病院には緩和ケアチームがあり、専門の医師、薬剤師、看護師などが各病棟をラウンドして患者さんの状態に合わせた支援をしています。
新人看護師のときは緩和ケアについて「がん患者さんの疼痛コントロールを支援するもの」というイメージを持っていました。がん患者さんの痛みがあったときに相談する。介入してもらい薬の調整をしてもらって痛みなどの苦痛を和らげる。そういった印象を持っていました。
緩和ケアについての印象が変わったのは緩和ケア医のH先生の存在でした。患者のAさんは末期の肺がん。さまざまな場所に転移していて体を動かすたびに痛みが出るためベッド上で生活し、いつ急変して亡くなるかわからない状態でした。
そんな患者さんと家族に、H先生は「お子さんたちもさ、いいって。これから準備して家、帰ろう!」と病棟スタッフを振り返ってニッ!と笑っていたのです。
私やそのほかの病棟看護師、主治医は「こんな状態なのに帰るの?!」と固まってしまいましたが「MSW(メディカルソーシャルワーカー)に連絡したら16時には介護用ベッド届くって」「往診医の先生も今日いいって」「訪問看護にサマリー!」とH先生の号令で一気に決まり、その日のうちに退院して自宅に帰って行ったのです。
「帰れない」と思っていた人の、ほんとうの願い
Aさんの「家族の家に帰りたい」という希望を現実にしたH先生。そもそもAさんは「やりたいことはない。ただただ痛みがなくなるといいんだけど」と私たちに話をしていました。入院患者さんには今後の希望を聞いたりするのですが、彼は自宅へ帰りたいとは言っていなかったので、「こんなに帰りたいと思っていたの?!」と当時の私は驚いていました。
本の一節にこうありました。
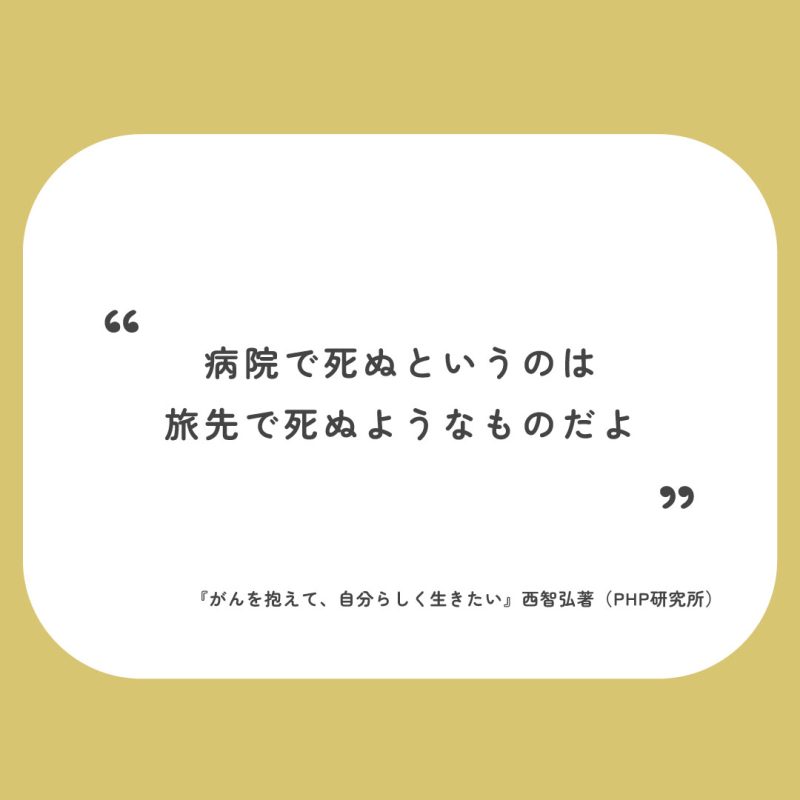
「家には家族がいるから」「安心するから」自宅に帰る理由についてこのような理由をよく聞いてきました。「旅先で死ぬ」という表現にとてもしっくりきたのを感じました。
旅先は自分の居場所から離れて新鮮な体験を得られる場所です。心と体がつらい中で自分の居場所から離れて過ごすことは、緩和ケアに限らず患者さんにとっては苦しいことなのだとあらためて感じました。
自分の状態では家に帰れない。痛みを取るのは病院で、痛いうちは家に帰れないと思いこんでいたAさん。そのため自宅に帰りたいと表出することがなかったんだなと気づきました。
「患者さん」じゃない、「Aさん」として
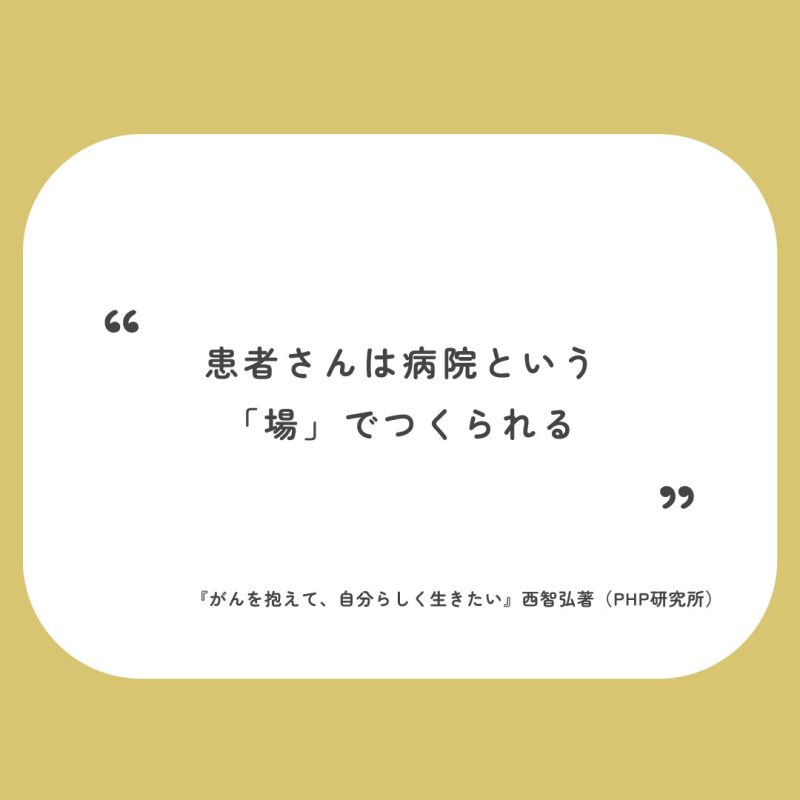
入院している人はもちろん患者さんなのですが、同時に「Aさん」という人であるという認識を持たなくてはいけないなと感じた言葉です。
今はがんによって動けない。私たちはがん患者さんであることに目が行きがちです。
進行度は?ADLは?急変のリスクは?症状、採血データ…「患者さん」はそういった病気とその内容がとにかく先行する言葉で、もちろん入院患者さんの治療や看護をするうえではとても大切な要素です。
しかし同時に「Aさん」であることもしっかり考えていくべきです。
子どもが3人。去年孫が産まれて写真をいつも眺めているAさん。
「いつでもいいので車椅子に乗せて欲しいです」と気遣いができるAさん。
「私たち兄弟で交代で協力するので何かあったらいつでも呼んでください」と話していたAさんの家族。
H先生はそういうAさんのひとりの人としての部分を把握して行動に移したんだなと感じました。
笑顔で退院して行ったAさんを思い出す
「Aさんの家族がありがとうございましたって言っていたのよ」
数週間後、MSWからAさんが亡くなったことと感謝を伝えてほしいという家族の言葉を聞きました。
私はそれを聞いて「ありがとうね」と嬉しそうにストレッチャーに乗ってバイバイと手をひらひらさせながら帰っていくAさんと
「緩和、こういうのがいいのよ」とつぶやくH先生を思い出したのでした。
▼紹介した本
『がんを抱えて、自分らしく生きたい』
西智弘著(PHP研究所)
※現在電子書籍のみ発売中
編集:白石弓夏
Nurse Life Mix 編集部です。「ライフスタイル」「キャリア」「ファッション」「勉強」「豆知識」など、ナースの人生をとりまくさまざまなトピックスをミックスさせて、今と未来がもっと楽しくなる情報を発信します。